
「こんなことで落ち込む自分」が、いちばんつらい
こんにちは、野村りなです。 出来事そのものよりも、「こんなことで落ち込んでいる自分」を意識した瞬間に、苦しさが増すことがあります。過去の私は、そんなことがよくありました。 続きをみる

こんにちは、野村りなです。 出来事そのものよりも、「こんなことで落ち込んでいる自分」を意識した瞬間に、苦しさが増すことがあります。過去の私は、そんなことがよくありました。 続きをみる

こんにちは、野村りなです。 落ち込んだり、苛立ったり、不安になったり。そうした感情が出てくると、「またこんな気持ちになってしまった」と、自分を責めてしまうことがあります。かつての私は、頻繁にそんなことがありました。 続きをみる
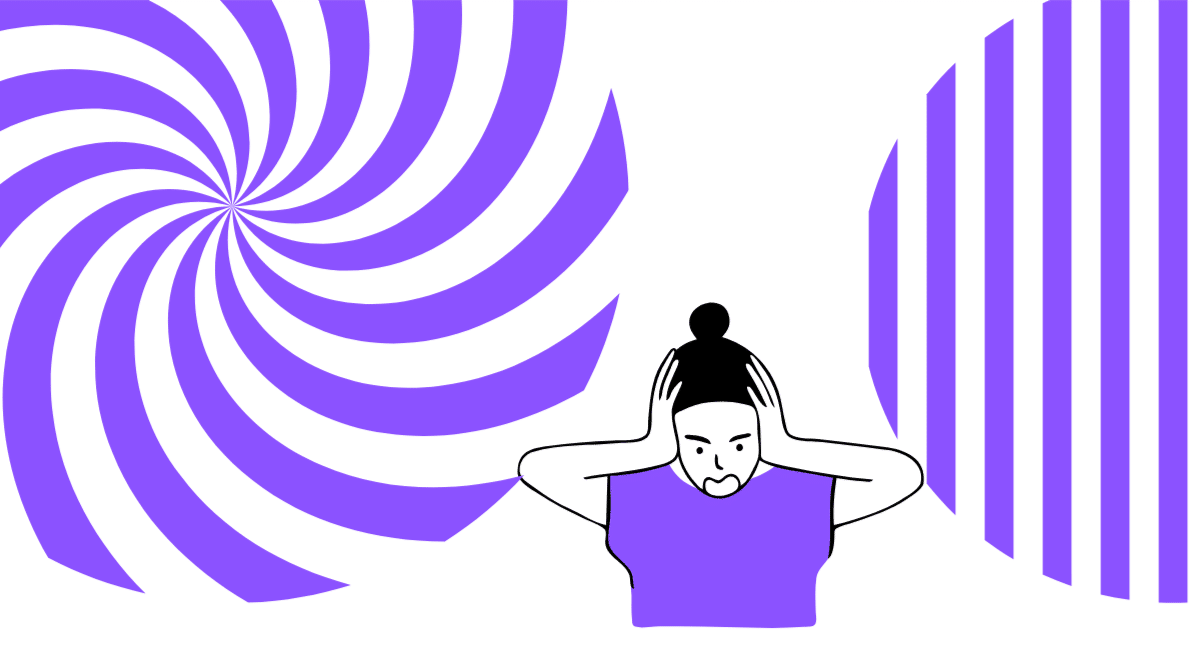
こんにちは、野村りなです。 人の感情に気づきやすい人ほど、疲れやすいのかもしれないと思うことがあります。私自身もまた、そんな人でした。 続きをみる

こんにちは、野村りなです。 これまでの章では、変わり続けるものを固定しようとするときに生まれる感覚や、「私」という感覚の揺らぎを見てきました。 続きをみる

こんにちは、野村りなです。 この章では、私自身の経験をもとに、「私が傷ついた」「私が評価された」「私が引き受けた」といった感覚が、どのように立ち上がってくるのかを振り返ってきました。出来事そのものよりも、「私」を前提にした解釈が、いつのまにか苦しさを生んでいた、という話でもあります。 続きをみる

こんにちは、野村りなです。 「自分に執着しない」「私を手放す」 続きをみる

こんにちは、野村りなです。 傷つかないように気をつけているのに、気づくと、前より苦しくなっている。そんな感覚を覚えたことがあります。 続きをみる
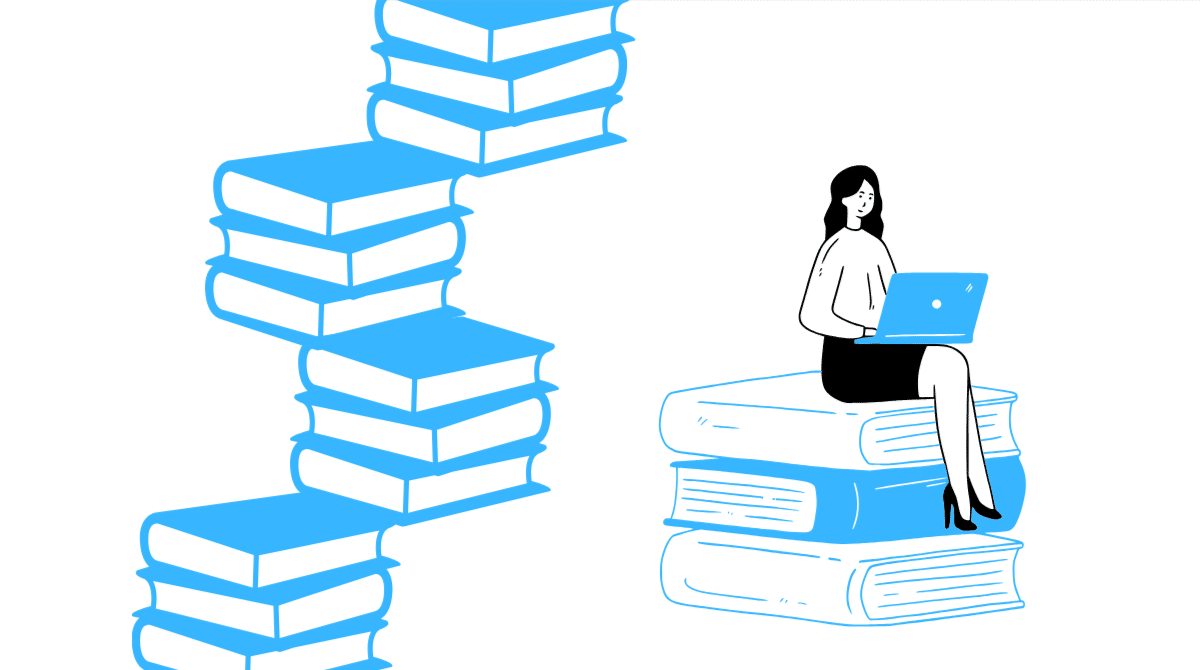
こんにちは、野村りなです。 仕事やチームの中で、自分の役割がはっきりしているときは、あまり意識しませんが、役割が曖昧になった瞬間に、落ち着かなくなることがあります。 続きをみる
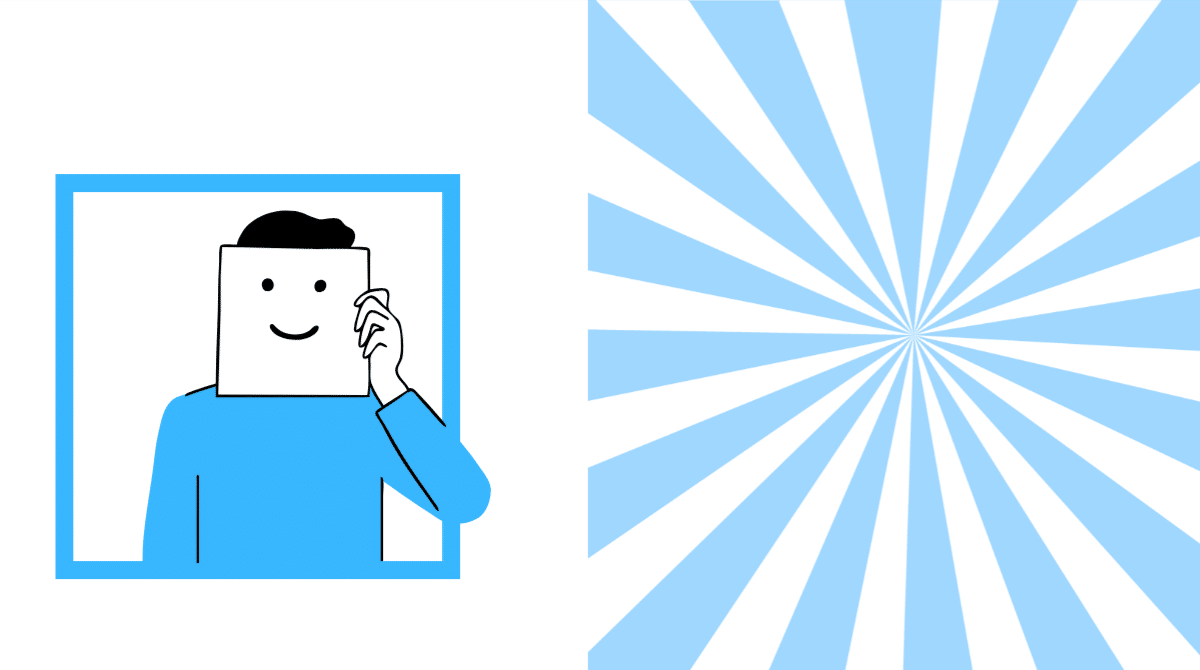
こんにちは、野村りなです。 チームで何かうまくいかなかったとき、「これは自分の問題だ」と感じてしまうことがあります。自分が直接ミスをしたわけではなくても、全体の流れが悪くなると、なぜか胸が重くなる。 続きをみる

こんにちは、野村りなです。 何か引っかかる出来事があったとき、「私だから、こうされたのだ」と感じてしまうことがあります。相手の態度や言葉に、はっきりした理由が見当たらなくても、その出来事が、私という存在に結びついて見えてくる。 続きをみる