視認性と直感性の言語論 — 「知っているのに分からない」からの脱却を目指して
私はこれまで、英語の学習に多くの時間と労力をかけてきました。文法を暗記し、単語やイディオムを覚え、試験対策にも励みました。TOEIC L&Rでは920点を取得し、読解力にもある程度の自信がつきました。それでも、「知っているのに分からない」という不思議な違和感がずっとつきまとっています。文章は読めるし、訳すこともできる。それなのに、頭の中に意味が直接飛び込んでくるような、そんな感覚がないのです。
母国語である日本語なら、文章を見た瞬間に意味が浮かび上がることがあります。直感的に内容を把握できるこの感覚が、英語にはなかなか現れないのです。
この違和感は、修士論文の執筆を通してより明確になりました。私は日本語と英語の論文を大量に読みましたが、明らかに処理の仕方に違いがありました。日本語論文であれば、タイトルや要旨をさっと読むだけで、その論文の主題や方向性が自然と頭に入ってきます。まさに、母国語である日本語ならではの「視認性」の高さを実感しました。しかし、英語論文になると、同じように目を通しても意味がすっと入ってこないのです。文字や単語が目に入っても、意味としてまとまらず、集中して読み込まなければなりません。これは明らかに、言語が「見える」かどうかの差であると感じました。
そんなとき、ビジネスパートナーとの会話で興味深い話を耳にしました。彼は最近、アプリを使ってゲーム感覚で楽しんで韓国語を学び始めたところ、韓国語の文字が「読める」というより「見える」と感じるようになったというのです。音と意味が直感的に結びつき、まるで母国語である日本語のように、自然に認識できる感覚が芽生えたといいます。彼はこの経験から、「視認性」と「直感性」という言語の性質に注目するようになったそうです。言葉を見た瞬間に意味が浮かぶ感覚、そして翻訳や理屈を介さず、感覚で理解する力。それが、視認性と直感性なのです。
英語と中国語を高いレベルで使いこなすその彼ですが、英語と中国語についてはその感覚はないそうです。彼にとって、英語や中国語は「勉強して身につけた言語」でした。文法や語彙を知識として蓄積し、それを使って意味を組み立てていくプロセスが必要でした。一方で韓国語は、文字の形や音、言葉のリズムといった「感覚」から入ったため、直感的な理解が生まれやすかったのだそうです。つまり、「学んだ言語」ではなく「慣れた言語」であり、まさに母国語である日本語のように自然に体に染み込んでいったのです。
この話から、私自身も言語習得における「アンラーニング(unlearning)」の重要性に気づかされました。知識として詰め込んだ英語を、もう一度ほどいて、感覚として再構築しなければ、本当の意味で「使える言語」にはならないのではないかと思ったのです。文法的に正しいかを常に気にするのではなく、「この場面ではこう言う」といった感覚に従う姿勢が大切です。言語は頭で覚えるものではなく、使いながら身につけるもの。母国語である日本語がそうであったように、見て、聞いて、話して、感じる中でこそ、「分かる」ようになるのではないでしょうか。
このような考えにふれた私は、英語へのアプローチを少しずつ変えようとしています。知識を手放し、感覚を信じること。それこそが、視認性と直観性の高い言語運用能力を育む鍵だと感じています。英語もまた、母国語である日本語のように、直感的に「見える」「感じられる」存在に変えていけるのではないかと、今はそう感じています。
余談ですが、実は高校時代、英語が全くできない状態で、1年間アメリカに交換留学した経験があります。選抜試験がマークシート形式だったため、偶然の合格。当然ながら、現地での生活は困難の連続でしたが、意地と根性でなんとか乗り切りました。言葉が通じない中でも私を温かく受け入れてくれたホストファミリーには、今でも感謝の気持ちでいっぱいです。それでも、現地で生活するうちに、やがて英語は「慣れた言語」になっていき、日常生活を送れるまでになりました。ただし、それは「勉強して身につけた言語」ではなかったため、帰国後の大学受験やTOEICでは苦戦し、ようやくそこで本格的な英語学習を始めたのです。

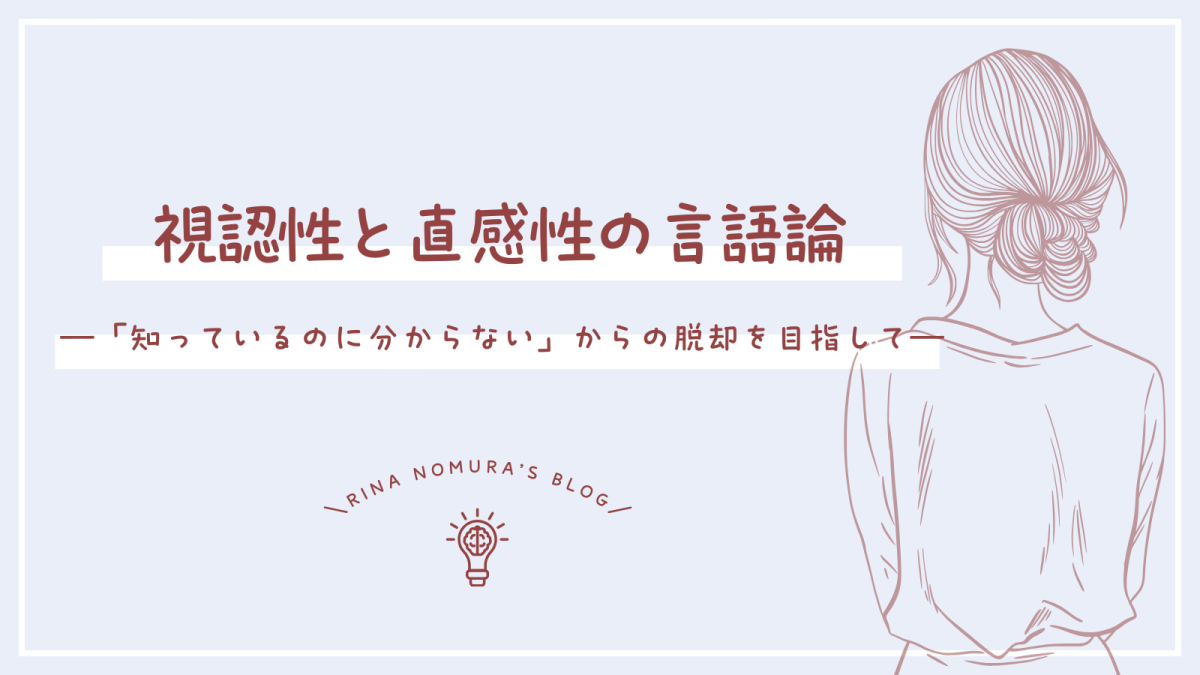

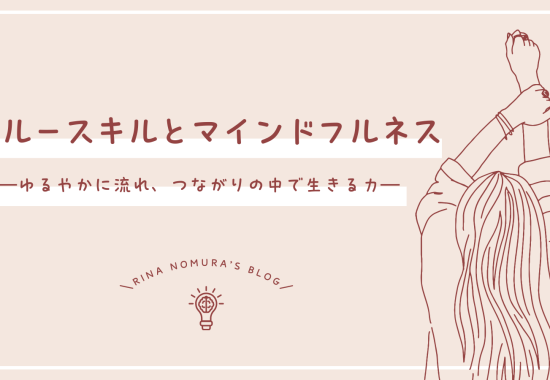
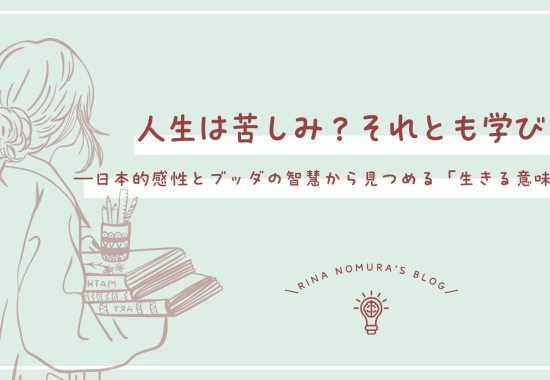
この記事へのコメントはありません。