第3回:分権の文化が変革を阻む—民主的組織に潜む「変われなさ」のミーム
第2回:事業は変わったのに企業文化は変われなかった——創業者ドリブンが通用しなくなるとき
前回は、強力な創業者主導の企業文化が、事業の多角化や顧客の変化に対応できなかった事例を紹介しました。 今回はその逆のケースです。
もともと「現場重視」「ボトムアップ」「自由な裁量」を大切にしてきた民主的な組織が、 いざ大きな変革が求められたとき、かえって意思決定が進まなくなる—— その背後にも、文化的ミームの働きがあります。
一見すると「活気があり、柔軟な会社」。しかし、なぜか肝心なところで組織が動かなくなる。 そこには、「分権の成功体験」から生まれたミームが、環境変化にブレーキをかけている構造があります。
それでは事例を見ていきましょう。
この企業は、製造業向けに小口の部品を大量に扱う専門商社です。
・顧客数:非常に多い
・取引単価:1件あたりは小さい
・商談期間:短く、即対応が求められる
・競合:多く、スピードと柔軟性が差別化要因
こうした事業では、現場が自律的に動けることが重要です。 実際、この企業は創業以来「現場への裁量委譲」を徹底してきました。
その結果、以下のような文化的ミームが組織内に定着していきます:
「お客様のことは現場が一番わかっている」
「管理よりもスピード」
「本社は現場の邪魔をしない」
「やり方は各現場ごとに違っていい」
これらのミームは、当時の事業モデルと完全に一致しており、組織を前進させる力として機能していました。
ところが近年、事業環境が大きく変化してきます。
・サプライチェーンの複雑化
・顧客からのEDI(Electronic Data Interchange:電子データ交換)対応要請
・働き方改革と人材流動化
これらに対応するため、在庫・注文・取引データなどの情報をシステムで統合する必要性が高まり、 企業としてもIT基盤への大規模な投資判断が求められるようになりました。
しかし、ここで組織は停滞に直面します。
「なぜ今のやり方を変える必要があるのか」
「現場に合わないシステムを入れても意味がない」
「導入するなら現場ごとにカスタマイズしてほしい」
という意見が各所から噴出し、経営会議は紛糾。 結果として、IT投資は「検討中」のまま数年間動かず、競合他社に遅れを取る事態となってしまいました。
この企業に残っていたのは、「現場の判断を尊重する」という強力な文化的ミームです。 本来は柔軟で自律的な組織運営を可能にするこの文化が、 「全社統合」「共通ルール」「大規模投資」のようなテーマに直面したとき、逆に足を引っ張る要因となったのです。
「自分の判断ではないから関わりたくない」
「文句は言うが代案は出さない」
「足並みが揃わないと動けない」
このような「責任の霧散」は、民主的な組織によく見られる文化の副作用です。 この局面で顕在化したミームを言葉にすると、以下のようになります:
「合意形成が最重要」
「失敗するくらいなら動かない方がいい」
「他部門に合わせるのは損」
このように、かつて有効だった文化的ミームが、別の環境においては変革を妨げる「逆機能」となるのです。

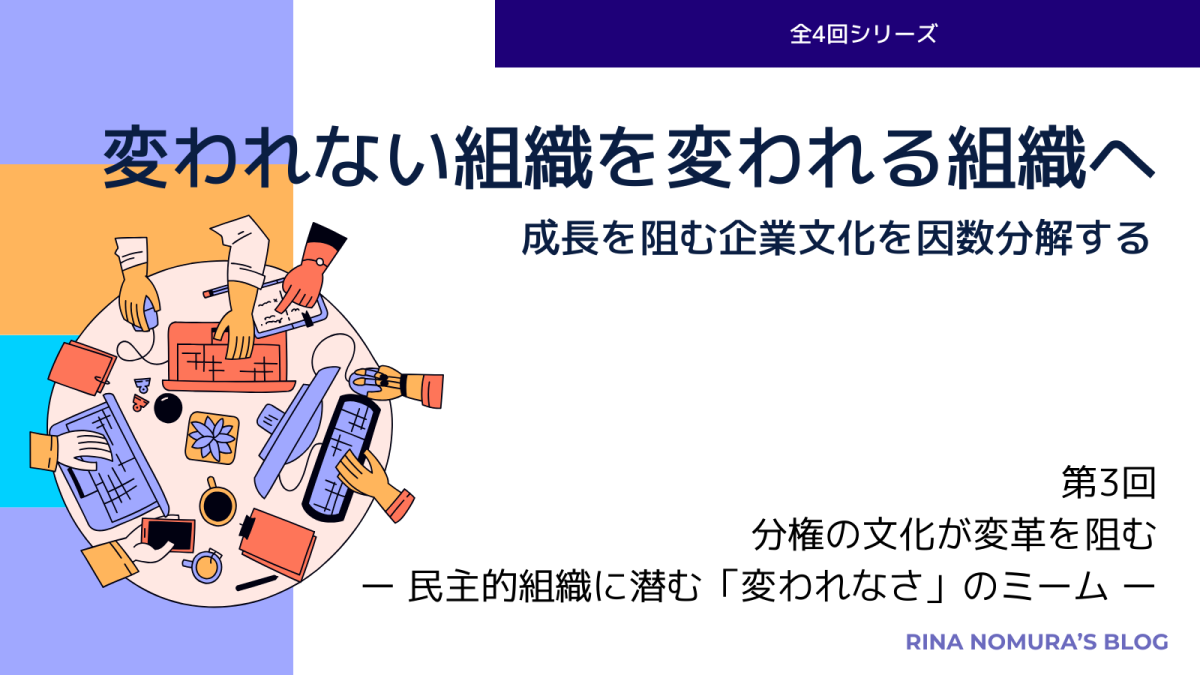


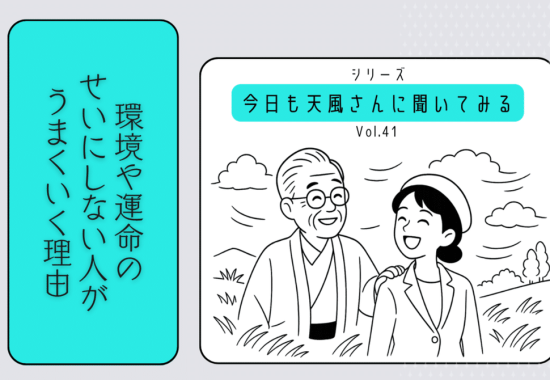
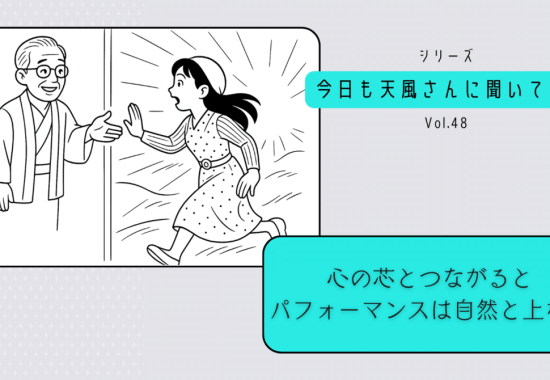


この記事へのコメントはありません。