第4回:「強さ」と「優しさ」のバランスを見つける—複雑で変化の激しい時代を生き抜くために
ーシリーズ「企業文化のジレンマ—優しさと強さのはざまで生産性と創造性を高めるために必要なこと」ー
第3回:「優しさ」と「強さ」のせめぎ合い—企業文化の分裂がもたらす課題
日本の企業文化は、高度成長期に築かれた「強さのインフラ」と、現代の価値観に基づく「優しさのインフラ」が交錯する中で、新たなバランスを模索しています。しかし、このギャップを埋めるには、単なる制度改革や意識改革だけではなく、一人ひとりが自分自身の感覚と向き合い、変化を受け入れることが不可欠です。
そのための第一歩として、以下の3つの視点が重要になると考えています。
私たちは無意識のうちに、自分の感覚が普遍的で正しいと思い込んでしまいがちです。特に、企業文化の中では「自分が育った環境ではこうだった」「自分はこれでうまくいった」という経験則が強く影響します。
しかし、それは必ずしも他の世代や価値観を持つ人々にとっての「正解」ではありません。例えば、上司が「厳しく叱るのは成長のため」と信じていても、受け手によっては「恐怖」として受け取られることがあります。また、若手社員が「心理的安全性があるから自由に意見を言っていい」と思っていても、上司からすれば「責任を取る覚悟のない軽率な発言」と感じられるかもしれません。
企業文化のギャップを乗り越えるには、まず「自分の感覚は絶対ではない」と認識し、異なる背景を持つ人々の感じ方を想像することが大切です。これは単に「相手の立場を考えよう」といった道徳的な話ではなく、多様な視点を理解すること自体が、組織の中でのストレスを減らす鍵となります。
次に重要なのは、「自分の感覚も常に変化する」ということを意識することです。人は、年齢や経験、置かれた環境によって価値観や感じ方が変わります。例えば、新入社員の頃は「もっと自由に意見を言いたい」と思っていた人が、いざ管理職になると「組織のまとまりが大事だ」と考えを改めることがあります。逆に、厳しく育てられた世代の人が、若手との関わりを通じて「優しさも必要だ」と気づくこともあるでしょう。
この「自分の感覚の変化」に気づくことで、過去の自分と今の自分のズレを理解できるようになります。それにより、他者の考え方にも柔軟になり、「自分も変わったのだから、相手も違う感じ方をするのは当然だ」と思えるようになります。そうすれば、企業文化の中で生じる「強さ」と「優しさ」のせめぎ合いにも、固定観念にとらわれずバランスを取ることができるでしょう。
最後に、最も大切なのは「自分の本当の感覚に気づくこと」です。企業文化の影響を受け、他者の価値観を考慮するうちに、「本当はどうしたいのか」が見えなくなることがあります。
しかし、他者に合わせるばかりでは、自分自身の軸がぶれてしまい、結果的にどちらの文化にも適応できずに苦しむことになります。たとえば、「本当は率直に意見を言いたいのに、相手を傷つけないように言葉を選びすぎて何も言えなくなっている」ことはないでしょうか。逆に、「本当はもっと穏やかに話したいのに、厳しくしないといけないと思い込んでいる」ことはないでしょうか。
こうした葛藤に向き合うことで、自分が「優しさ」と「強さ」のどこに立ちたいのかが見えてきます。それが明確になれば、周囲の環境に振り回されることなく、自分なりのバランスを持って行動できるようになります。
日本の企業文化は、「優しさ」と「強さ」のはざまで揺れ動いています。どちらかに完全に偏るのではなく、その中間にある「柔軟性」が、今後の組織の鍵となるでしょう。
それを実現するためには、一人一人が、「自分の感覚が全てではないことを知る」 ことが第一歩です。次に、「自分の感覚も変化することを知る」 ことで、他者との違いを受け入れる余裕が生まれます。そして最後に、「自分の本当の感覚に気づく」 ことで、自分がどのような立場を取りたいのか自ずと明らかになり、バランスの取れた思考や行動につながります。
このプロセスを経ることで、「優しさのインフラ」と「強さのインフラ」のどちらにも縛られない、新しい働き方が見えてくるのではないでしょうか。
企業文化の変化はすぐには訪れないかもしれません。しかし、一人一人が自分の立ち位置を見つけることができれば、どんな環境でも柔軟に適応しながら、自分らしい働き方を実現できるはずです。
本シリーズを通じて、企業文化の変化に向き合うヒントをお届けしてきました。これからの時代に合った新しい働き方を、一人ひとりが模索していくことが、より良い組織づくりへの第一歩になるのではないでしょうか。

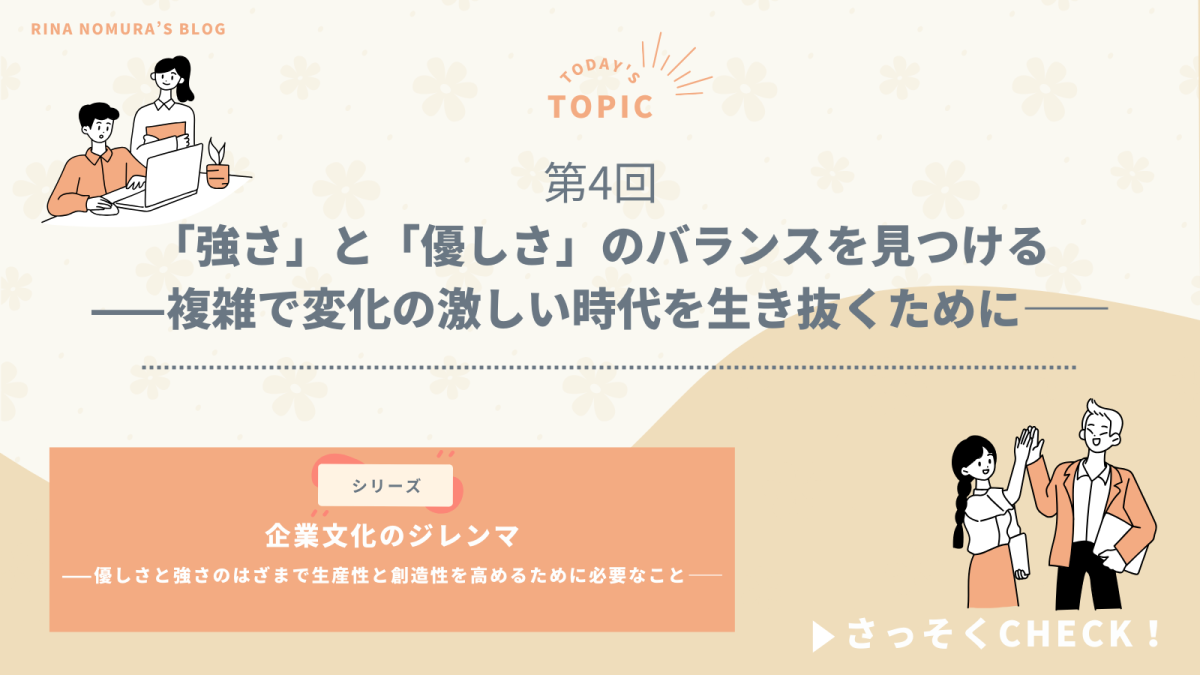
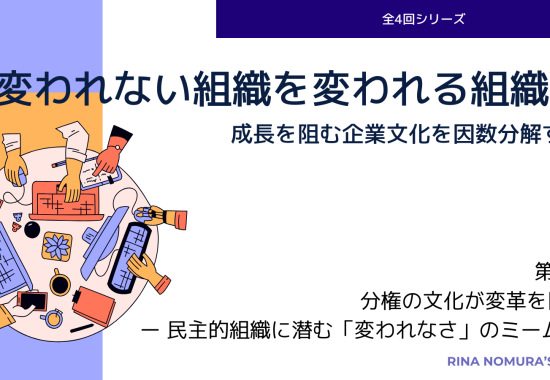
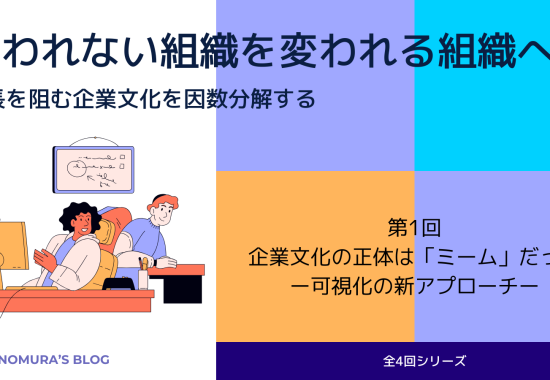
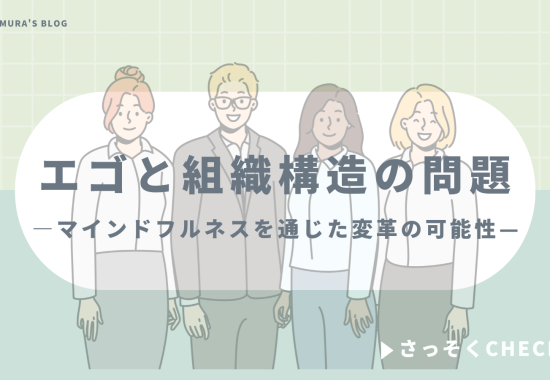
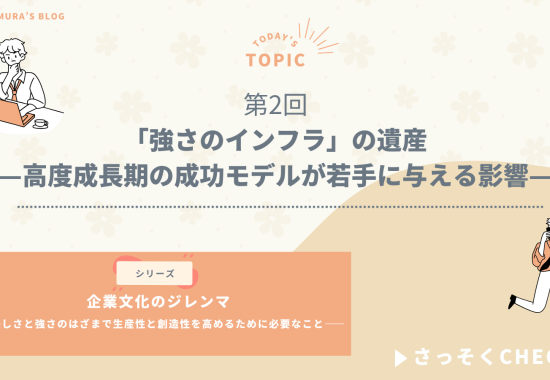
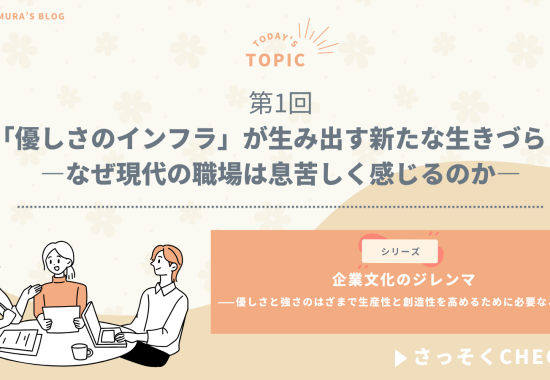
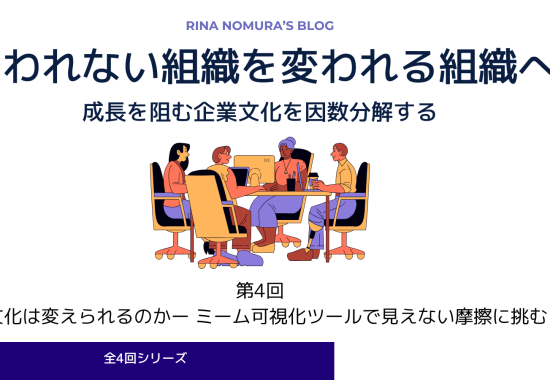
この記事へのコメントはありません。