第1回:「優しさのインフラ」が生み出す新たな生きづらさ—なぜ現代の職場は息苦しく感じるのか
ーシリーズ「企業文化のジレンマ—優しさと強さのはざまで生産性と創造性を高めるために必要なこと」ー
はじめに
私は、上場企業で17年間勤務したのち、企業向けマインドフルネス研修事業・創業経営者向けコーチング事業を立ち上げました。さまざまな企業の現場に関わる中で、組織文化や人間関係における課題、そしてそれが生産性や創造性に与える影響を目の当たりにしてきました。
現代の企業文化は、「優しさ」と「強さ」という二つの価値観の間で揺れ動いています。心理的安全性や共感が重視される一方で、高度成長期に根付いた「耐えること」「率直に物を言う文化」が今なお影響を与えています。この二つの相反する価値観が共存することで、多くの人がどちらに適応すればよいのか戸惑い、時にストレスを感じることも少なくありません。
このシリーズでは、企業文化の変遷と現代におけるジレンマを4回にわたって考察し、どのように「優しさ」と「強さ」のバランスをとりながら、より良い働き方や組織を築いていけるのかを探っていきます。
第1回は「『優しさのインフラ』が生み出す新たな生きづらさ—なぜ現代の職場は息苦しく感じるのか」です。近年、企業文化では「優しさ」や「共感力」が重視され、職場の心理的安全性が求められるようになりました。しかし、この「優しさの基準」が高まることで、そこに適応できない人々が新たな生きづらさを感じています。「優しくあるべき」というプレッシャーがどのように人間関係を変化させているのかを考えます。
第2回は「『強さのインフラ』の遺産—高度成長期の成功モデルが若手に与える影響」です。日本の企業文化には、高度成長期に築かれた「強さのインフラ」が今も残っています。長時間労働や厳しい指導、ストレス耐性の重視といった価値観が、現代の働き手にどのような影響を与えているのかを掘り下げます。
第3回は「『優しさ』と『強さ』のせめぎ合い—企業文化の分裂がもたらす課題」です。「心理的安全性」を重視する動きがある一方で、「厳しさ」や「率直な物言い」が企業文化に根強く残っている現状。この二重構造が生むジレンマや、世代間の認識の違いについて考察します。
第4回は「『強さ』と『優しさ』のバランスを見つける——変化する企業社会を生き抜くために」です。企業文化の変化に適応しながら、自分らしく働くためのヒントを探ります。「強さ」と「優しさ」のどちらかに偏るのではなく、それらを共存させる新しいアプローチとはどのようなものでしょうか。 一人ひとりが取りうる行動について考えていきます。
企業文化の変化は一朝一夕には起こりません。しかし、自分の価値観や働き方を見直すことで、変化の波を乗りこなすことは可能です。本シリーズが、より良い職場環境を築くためのヒントになれば幸いです。
第1回:「優しさのインフラ」が生み出す新たな生きづらさ—なぜ現代の職場は息苦しく感じるのか
私たちが日々利用する社会インフラ。たとえば道路、公共交通機関、教育制度などは、平均的なニーズに合わせて設計されています。これは効率性を追求する上では理にかなっていますが、一方で「平均から外れた人」にとっては不便や困難を生むこともあります。
同じことが、人間関係のインフラにも言えるのではないでしょうか。社会が求める「理想的な人間関係」も、時代とともに変化しながら、ある種の平均値へと収束していきます。特に現代では、「優しさ」や「共感力」が重視され、SNSや企業の価値観においても「思いやりのある行動」や「多様性の尊重」が強く求められるようになりました。
これは社会全体としては良い傾向ですが、一方で「優しさの基準」が高まることで、そこに適応できない人にとっては新たな生きづらさが生まれています。
かつて、人付き合いのルールは比較的シンプルでした。相手を傷つけてしまったら謝る、困っている人がいたら助ける、といった基本的なことを押さえていれば、社会に適応できました。しかし、今は「相手の感情に細やかに気を配ること」や「傷つけない言葉を選ぶこと」が求められ、それを満たせない人は「配慮が足りない」「空気が読めない」と見なされがちです。
たとえば、発達特性の関係で他者の感情を読み取ることが苦手な人や、対人関係の距離感をつかむのが難しい人にとって、この「優しさの基準」は非常に高いハードルになります。悪意があるわけではなく、ただ「平均的な優しさ」に到達できないだけなのに、無意識に排除されてしまうことがあるのです。
また、忙しさやストレスで余裕がないときにまで「優しくあるべき」というプレッシャーがかかると、心の負担になってしまいます。
現在の若者は、多くの生きづらさを抱えていると言われています。たとえば、こども家庭庁が実施した「我が国と諸外国のこどもと若者の意識に関する調査」(令和5年度)では、日本、アメリカ、ドイツ、フランス、スウェーデンの若者対象に調査が行われています。「自分自身に満足している」、「自分には長所があると感じている」、「今の自分が好きだ」、「自分の考えをはっきり相手に伝えることができる」、「うまくいくかわからないことにも意欲的に取り組む」、「自分は役に立たないと強く感じる」という質問項目に対して、日本の若者は、他国の若者と比較して低い水準にあるという結果が出ており、さまざまな生きづらさを抱えていることが浮き彫りになっています。
その背景の一つには、「優しさ」の定義が一義的になり、かつ「優しさの基準」が高まったため、人間関係のインフラから押し出される感覚があるのではないでしょうか。少しでも気遣いが足りなかったり、共感が浅かったりすると、すぐに「配慮が足りない人」とラベリングされてしまう。また、SNS上では模範的な優しさを持つ人の言動が可視化され、「あの人はこんなに気遣いができるのに、私はできていない」と自己嫌悪に陥ることもあります。
かつては「優しい人がいる」という状態が特別だったのに対し、今は「誰もが優しくあるべき」が前提になっています。この変化が、平均に到達できない人を「不適応」と感じさせ、優しさが「選択」ではなく「義務」になったとき、人は疲れてしまうのです。
もちろん、優しさが社会の基準となること自体は、決して悪いことではありません。むしろ、過去に比べて思いやりを大切にする社会になったことは大きな進歩です。しかし、優しさが一律の基準として適用されると、人間関係のインフラにおいても「平均から外れること」がリスクになってしまいます。
では、どうすればよいのでしょうか。
一つの答えは、「優しさの多様性を認めること」だと思います。すべての人が同じ形の優しさを持っているわけではなく、それぞれの特性や状況によって表現の仕方は異なるはずです。「察する優しさ」もあれば、「率直に指摘する優しさ」もありますし、「距離を取る優しさ」もあります。
こうした多様性を受け入れ、「優しさの平均値」を押し付けすぎないことが、現代の生きづらさを和らげる一歩になるのではないでしょうか。
実際には、多くの場合、私たちは無意識のうちに「平均」を強制してしまっているものです。そして、そのことに自覚的である人は意外と少ないのではないでしょうか。まずは、「自分もまた、どこかで他者に優しさの基準を押し付けていないか」と問い直してみることが重要かもしれません。
次回は、「第2回『強さのインフラ』の遺産—高度成長期の成功モデルが若手に与える影響」について考察していきます。

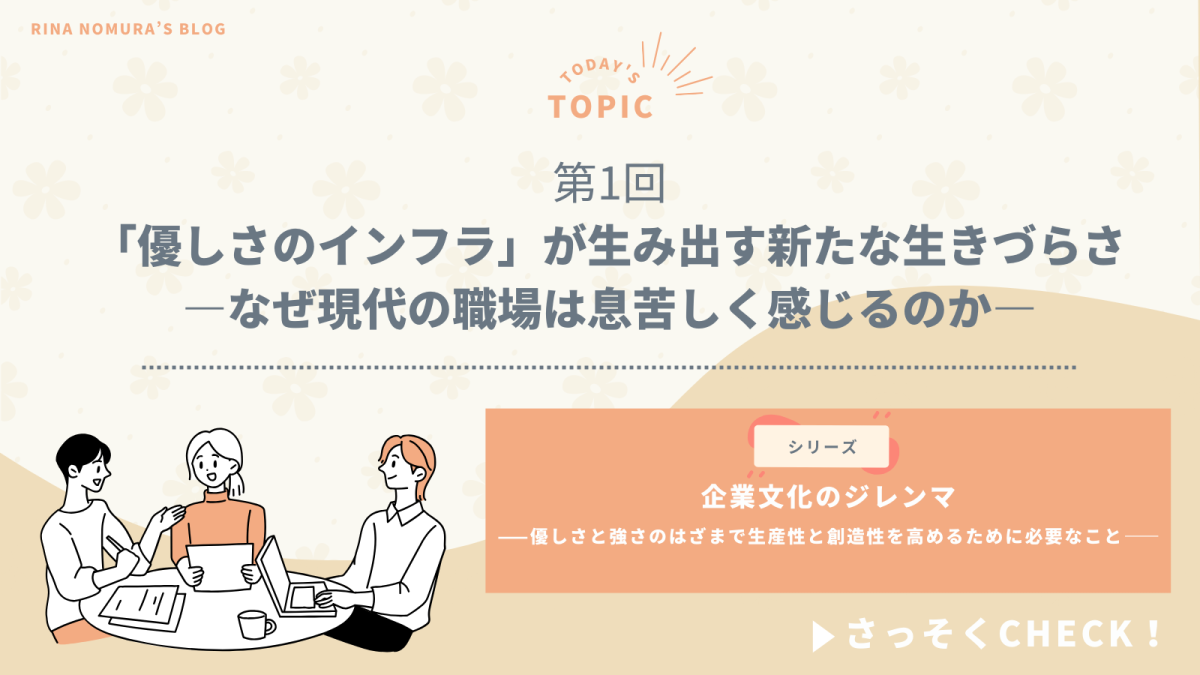
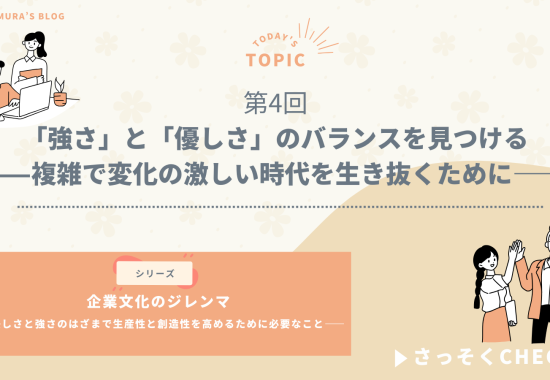
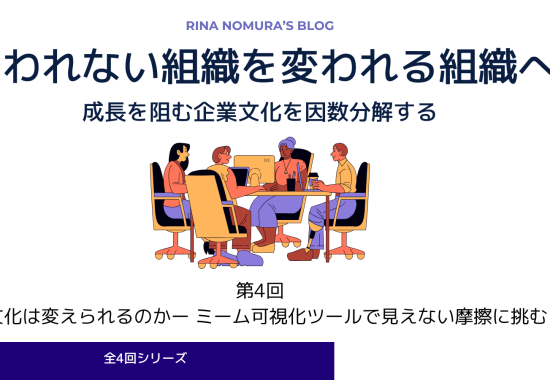
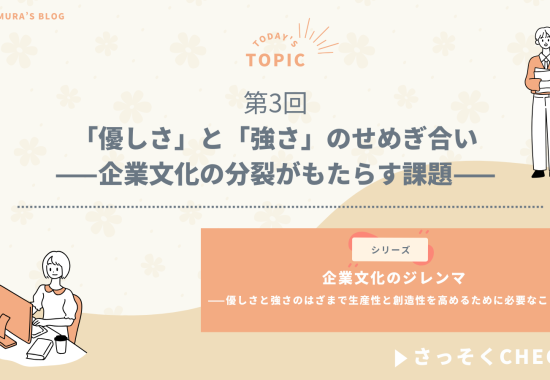
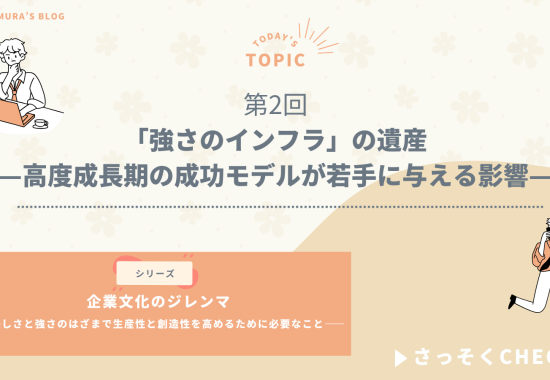

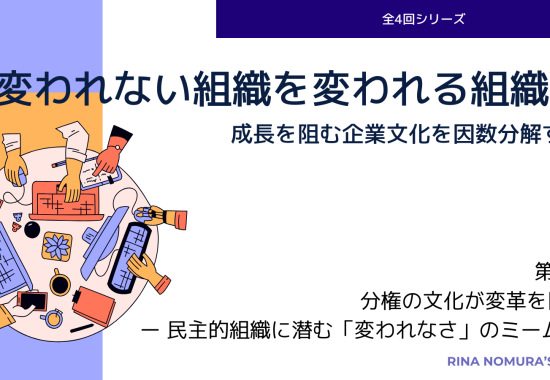
この記事へのコメントはありません。