第2回:「強さのインフラ」の遺産—高度成長期の成功モデルが若手に与える影響
ーシリーズ「企業文化のジレンマ—優しさと強さのはざまで生産性と創造性を高めるために必要なこと」ー
第1回:「優しさのインフラ」が生み出す新たな生きづらさ—なぜ現代の職場は息苦しく感じるのか
日本の企業文化には、他国にはあまり見られない独特の「強さのインフラ」が存在します。それは、高度成長期を支えた世代——ストレスに強く、合理性よりも忍耐と努力を重視する人々によって築かれたシステムです。この世代は、戦後の復興から経済成長をけん引し、世界に誇れる「日本的経営」を生み出しました。
高度経済成長期からバブル期、そしてその余波が続いた時代は、経済成長を支える企業が社会の基盤となっていた時代です。この時代において、仕事とは「厳しくともやり抜くもの」であり、ストレスは「耐えるもの」でした。長時間労働は当然とされ、組織の結束力が何よりも重視されました。個人のキャリアよりも「会社に尽くす」ことが求められ、成果以上に努力や忠誠心が評価される文化が根付いていったのです。
また、「率直にモノを言う」ことも重要視されていました。部下に厳しい言葉を投げかけるのは「鍛えるため」、上司が部下を叱るのは「育てるため」。こうした指導スタイルは、組織を強くするための手段とされていました。
この「強さのインフラ」は、日本企業を世界レベルの競争に耐えうる組織へと押し上げました。しかし、かつて企業が社会の基盤となり経済成長を支えていた時代とは異なり、現代は個人の選択肢が広がり、多様な価値観が共存する社会へと変化しています。その結果、この「強さ」は形を変え、若者たちに新たな課題をもたらすようになっています。
現代の日本は、高度成長期とは異なり、成熟した社会へと移行しました。若者たちの価値観も変化し、「耐えること」よりも「意味のあること」に価値を見出し、「努力」よりも「成果」を重視する傾向が強まっています。たとえば、効率を重視する「タイパ(タイムパフォーマンス)」という考え方の広まりは、その象徴的な例でしょう。
また、「率直な物言い」はパワーハラスメントとされ、メンタルヘルスへの配慮が重視されるようになりました。しかし、多くの企業にはいまだに「強さのインフラ」が根強く残っています。そのため、若者たちは「何が正解かわからない」状況に直面することが少なくありません。
一方では「意見を言え」と求められ、もう一方では「空気を読め」と言われる。心理的安全性を重視する時代になったとはいえ、組織の中にはいまだ「率直にものを言う文化」が残っており、そのギャップに適応できない若者は「メンタルが弱い」「使えない」と評価されてしまうこともあります。
さらに、ストレス耐性の高さが求められる職場では、「耐えられないこと」が個人の問題とされがちです。「働き方改革」や「ワークライフバランス」の重要性が語られる一方で、現場では「少しのことで弱音を吐くな」という暗黙の圧力が残っているのが現実です。実際、私のクライアント企業でも、「レジリエンス(回復力)」をテーマにした研修の要望は多く、企業が依然として「耐える力」を重視していることがうかがえます。
それでは、日本の企業文化は今後どのように変わっていくべきなのでしょうか。
一つの方向性として、「強さのインフラ」から「柔軟さのインフラ」へとシフトすることが挙げられます。過去の成功体験に固執するのではなく、新しい価値観に適応できる能力を、組織全体が持つことが求められます。
例えば、「耐える」ことが評価されるのではなく、「工夫すること」が評価される仕組みへ。「率直に言う」ことが重要なのではなく、「適切に伝える」ことが重視される文化へ。そうした変化がなければ、若者たちは企業文化に適応することが難しくなり、結果的に企業の競争力そのものが低下する可能性があります。
高度成長期を支えた世代が作り上げたインフラは、日本を強くしました。しかし、時代が変われば、求められるインフラも変わります。「強さ」だけでなく、「柔軟さ」を持つことで、新しい世代にとっての「生きやすい環境」を整えることが、今後の日本企業にとって重要な課題となるのではないでしょうか。
次回は、「第3回:『優しさ』と『強さ』のせめぎ合い—企業文化の分裂がもたらす課題」というテーマで考察していきます。

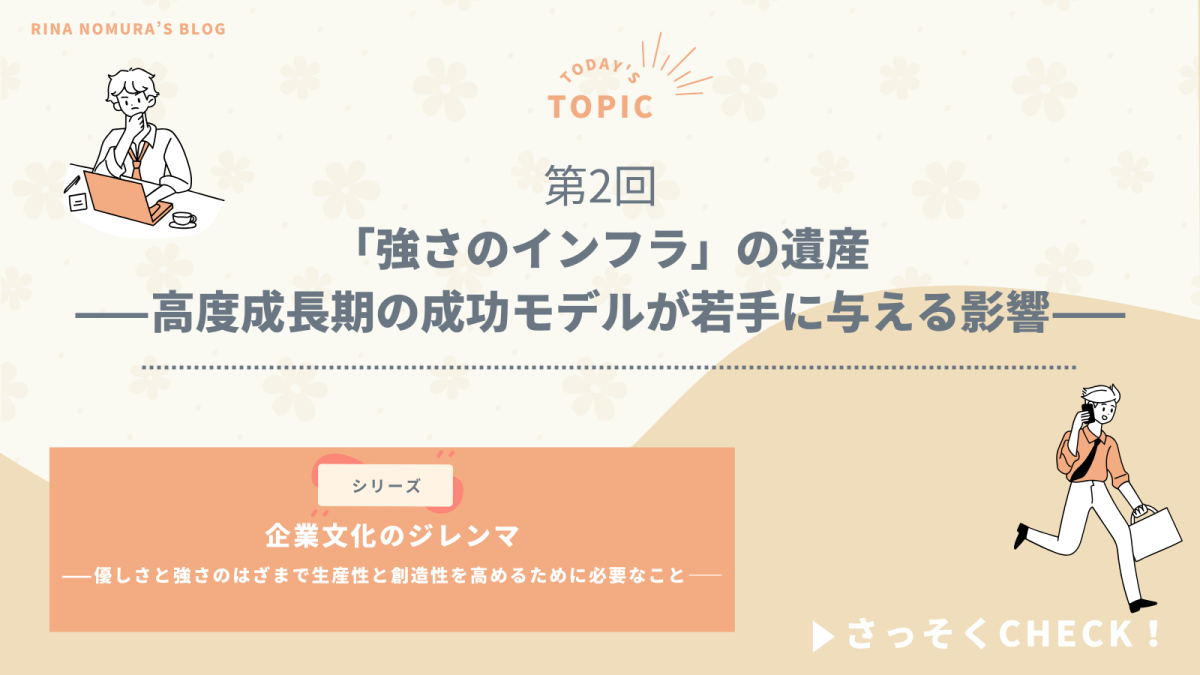
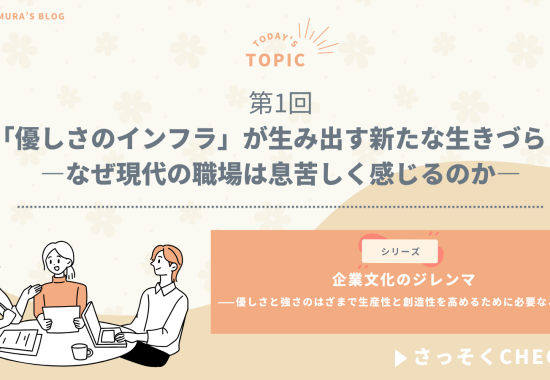
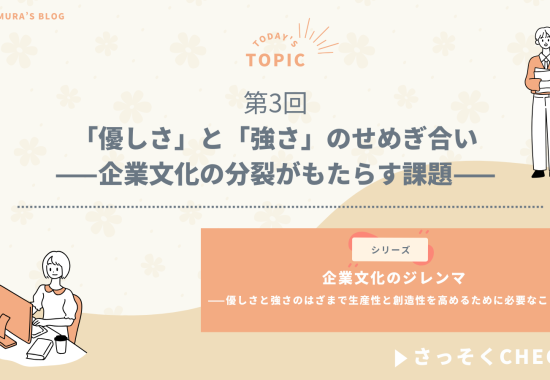
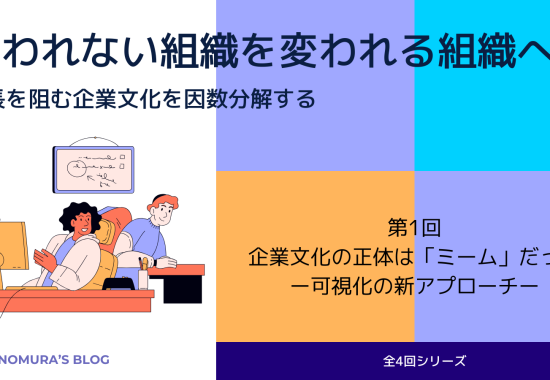
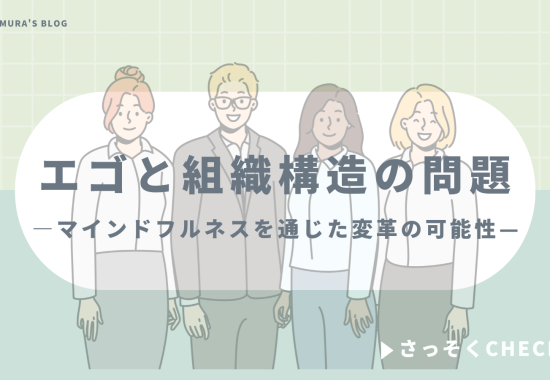
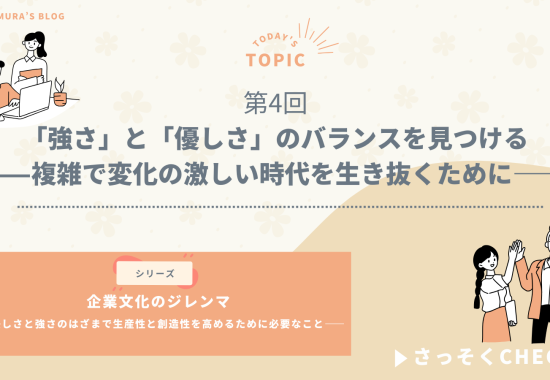

この記事へのコメントはありません。