第5回:浅い理解と深い理解 ー「すぐにわかろうとすること」の危うさ
【シリーズエッセイ(全9回)】意味・意識・AI・人間ーAI時代にマインドフルネスが必要な理由ー
これまで、人間は脳のエネルギー効率を守るために、
情報を減らし、既存のモデルに頼ろうとする傾向があることを見てきました。
今回はそこからさらに踏み込み、
「浅い理解」と「深い理解」の違いについて考えてみたいと思います。
私たちは日常生活のなかで、できるだけ早く物事を理解し、
答えを出そうとする習慣が身についています。
ビジネスの現場では即断即決が求められ、
学校教育でも、正解を素早く出すことが評価されることが多いでしょう。
しかし、こうした「すぐにわかろうとする姿勢」には、思わぬ落とし穴があります。
心理学では、浅い理解と深い理解の違いを指摘する研究があります。
たとえば、Biggs(1987)の**学習アプローチ理論(Approaches to Learning)**によれば、
-
浅いアプローチ(Surface Approach)は、情報を丸暗記し、表面的に処理する傾向を持ち、
-
深いアプローチ(Deep Approach)は、概念同士の関連を探し、意味を理解しようとする態度を指します。
浅いアプローチでは、
目の前のタスクを早く終わらせることが優先され、
結果として、知識は短期間で忘れ去られたり、応用が効かなかったりします。
一方、深いアプローチでは、
時間がかかっても、「このことは、どういう意味を持っているのか?」と問い続けながら学びます。
その結果、理解はより本質的なものとなり、応用や創造につながるのです。
この違いは、対話やコミュニケーションにもあらわれます。
たとえば、誰かの意見を聞いたときに、
すぐに自分の知っているフレームに当てはめて判断してしまうことはないでしょうか?
-
「つまりこういうことね」と早合点する
-
「それはこういう意味だろう」と決めつける
これは脳にとっては楽なやり方ですが、
相手が本当に伝えたかった微細なニュアンスや、背景にある複雑な文脈を見落としてしまうリスクをはらんでいます。
本当に意味を理解するとは、
すぐに確信を持たないことでもあります。
深い理解とは、
-
「まだ完全にはわからない」
-
「もう少し考えたい」
-
「この背後に別の可能性があるかもしれない」
という態度を持ちながら、
情報をじっくり咀嚼し、時間をかけて内側で育てていく営みです。
この態度は、直感的には「非効率」に思えるかもしれません。
しかし、真に新しい発見や、豊かな対話は、
この“もどかしい間”を恐れずに保つ力から生まれるのです。
本当に意味を理解するとは、
すぐに答えを出すことではありません。
深い理解とは、
-
「まだ完全にはわからない」
-
「もう少し考えたい」
-
「この背後に別の可能性があるかもしれない」
そんな思いを抱きながら、
急がず、焦らず、モヤモヤを抱えたままにしておくことです。
もやもやを抱え続ける勇気こそが、
新しい意味や洞察を生み出す土壌になります。
直感的には「非効率」に見えるかもしれませんが、
この「もどかしい間」を大切にすることで、
より豊かな対話や発見が生まれていくのです。
次回(第6回)では、
この「わからなさに耐える力」を育む方法として、
マインドフルネスや瞑想の役割について考えていきます。
ぜひ引き続きご覧ください!
参考文献
Biggs, J. (1987). Student Approaches to Learning and Studying. Australian Council for Educational Research.

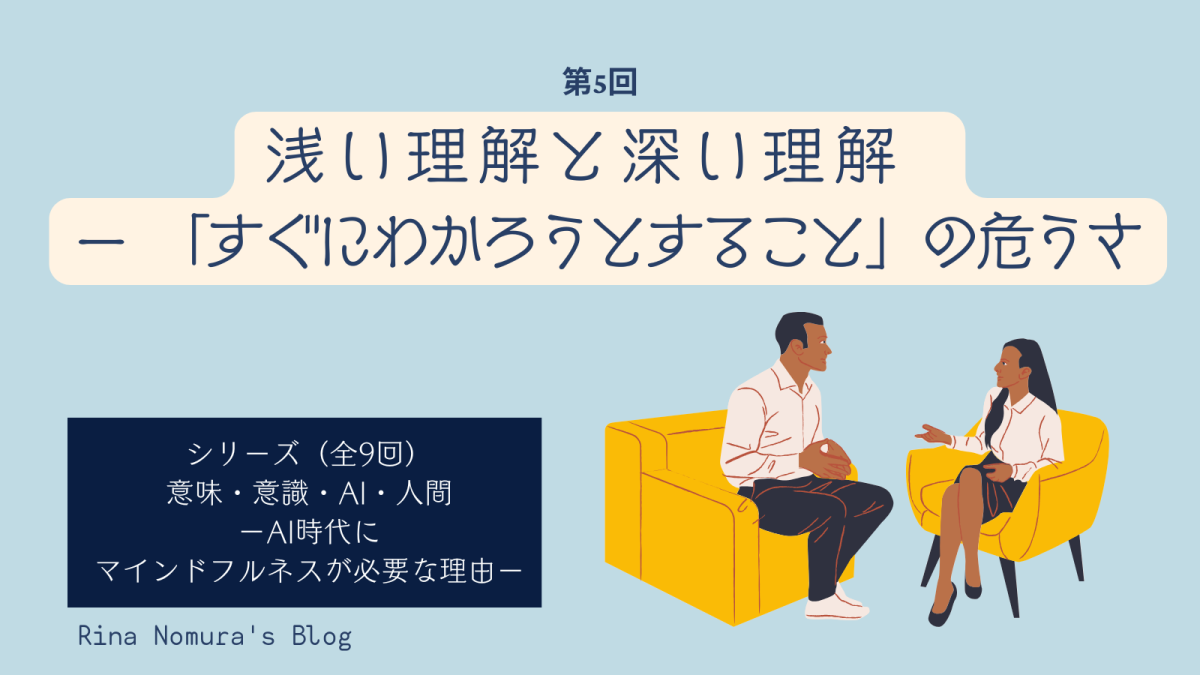
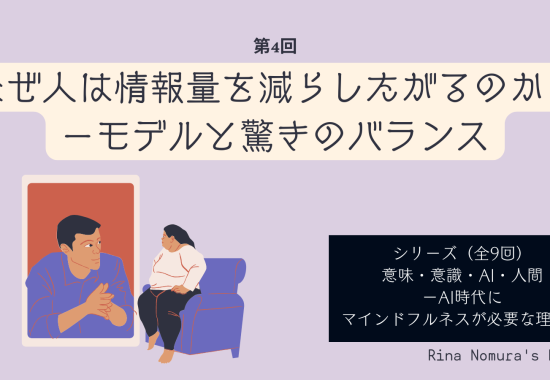
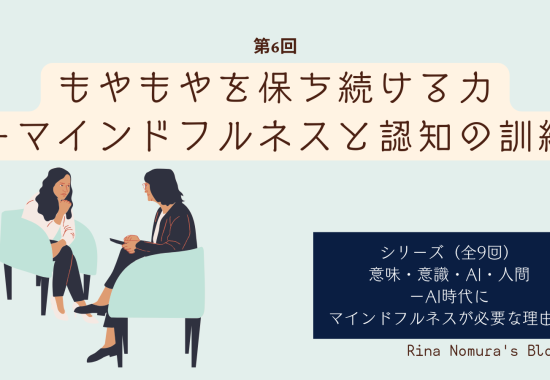
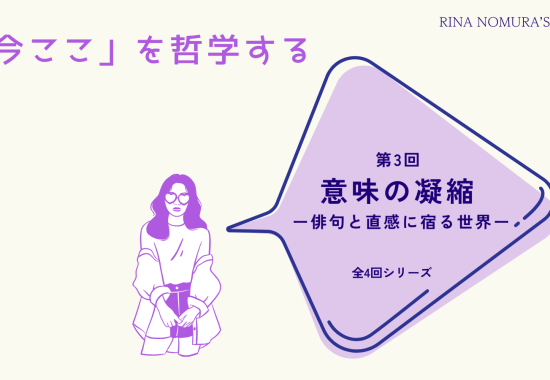
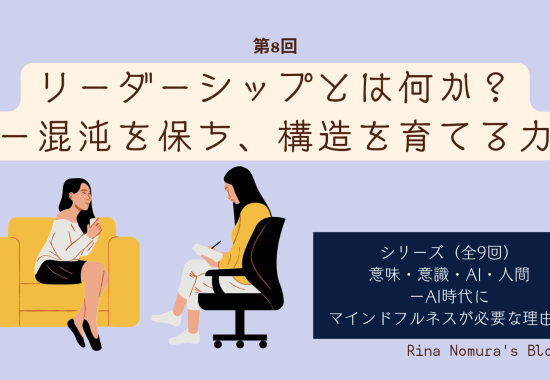
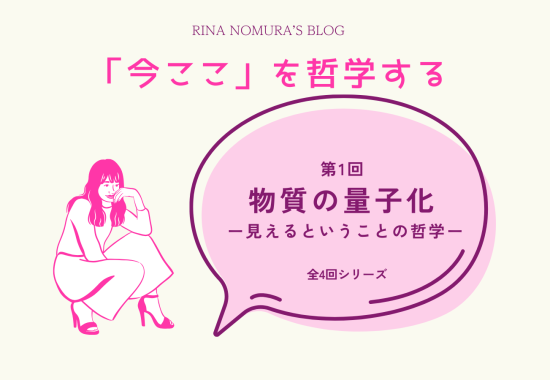
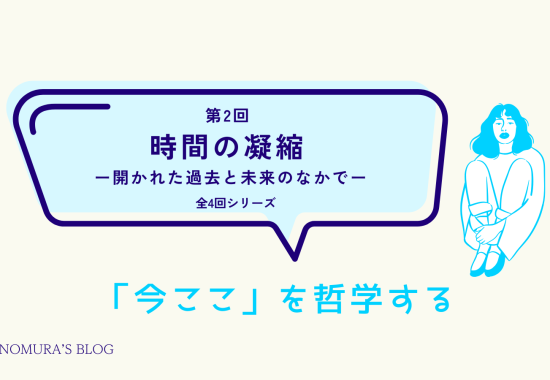
この記事へのコメントはありません。