第2回:情報理論ってなんだろう? ー 意味とノイズのしくみ
【シリーズエッセイ(全9回)】意味・意識・AI・人間ーAI時代にマインドフルネスが必要な理由ー
「情報」とは、そもそも何なのでしょうか?
この問いに科学的に挑んだのが、1948年にクロード・シャノンが発表した論文『A Mathematical Theory of Communication』です。
シャノンは、「情報」という概念を数学的に定義し、数式で扱えるようにしました。
彼によれば、「情報量」とは「予測のしにくさ」と言い換えることができます。
たとえば、コイントスの結果(表か裏)は、事前には予測できないため、1回ごとの情報量は大きい。
一方で、「明日は月曜日です」といった予測しやすい内容は、情報量としては小さくなります。
意外性が高いほど、情報量は大きい――。
この考え方は、現代のインターネット通信、スマートフォン、暗号技術など、
あらゆる情報社会の基盤となっています。
情報理論は「いかに情報を効率よく、正確に送るか」を追求する技術的な理論です。
たとえば、ノイズが入ったときにもできるだけ正しくメッセージを復元できるよう、
符号化や訂正の仕組みが考案されました。
しかし、ここで重要なポイントがあります。
それは、情報理論は「意味」には踏み込まないという点です。
シャノン自身も論文の中で次のように述べています。
“The semantic aspects of communication are irrelevant to the engineering problem.”
(通信における意味的側面は、工学的な問題にとっては無関係である。)
つまり、情報理論は「どのように記号を効率よく送るか」という工学的問題に取り組むものですが、
その記号が受け手にとってどんな意味を持つかには関与しないのです。
たとえば、「犬」という単語を送ることはできます。
しかし、その単語から何を思い浮かべるかは人によって異なります。
子どものころ飼っていた犬を思い出す人もいれば、警察犬や比喩表現として受け取る人もいるかもしれません。
同じ情報が送信されても、そこから立ち上がる意味は、
受け手の経験や価値観によって大きく変わってくるのです。
この違いを踏まえて、現代では「セマンティック情報(意味のある情報)」という概念が重視されるようになりました。
単なる記号ではなく、受け手の内側で何らかの再構成を促す情報こそが、意味のある情報だと考えられています。
さらに、人間同士の対話では、
情報の正確な伝達を妨げる「ノイズ」も、単なる技術的な問題にとどまりません。
たとえば、
-
技術的なノイズ(音声の乱れ、回線の不安定)
-
感情的なノイズ(怒り、不安、警戒心)
-
認知的なノイズ(言葉の定義の違い、文化のギャップ)
など、さまざまな形で「意味の伝達」を阻害する要素が存在します。
情報理論の世界では、ノイズを排除する工夫が重ねられてきました。
しかし、人間の対話においては、ノイズを敵視するのではなく、そこに込められた違いや背景を読み取ろうとする姿勢が求められるのです。
情報をただ送るのではなく、
違いを受けとめ、ノイズを越えて、
新たな意味を共に育てていくこと。
それが、現代における「伝える」という営みの、本当の難しさであり、醍醐味なのかもしれません。
次回(第3回)では、
「なぜ私たちの話はすれ違うのか?」という問いを出発点に、
ノイズと考え方の違いについて、さらに深く考えていきます。
ぜひ引き続きご覧ください!
参考文献
Shannon, C. E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. Bell System Technical Journal, 27(3), 379–423.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x

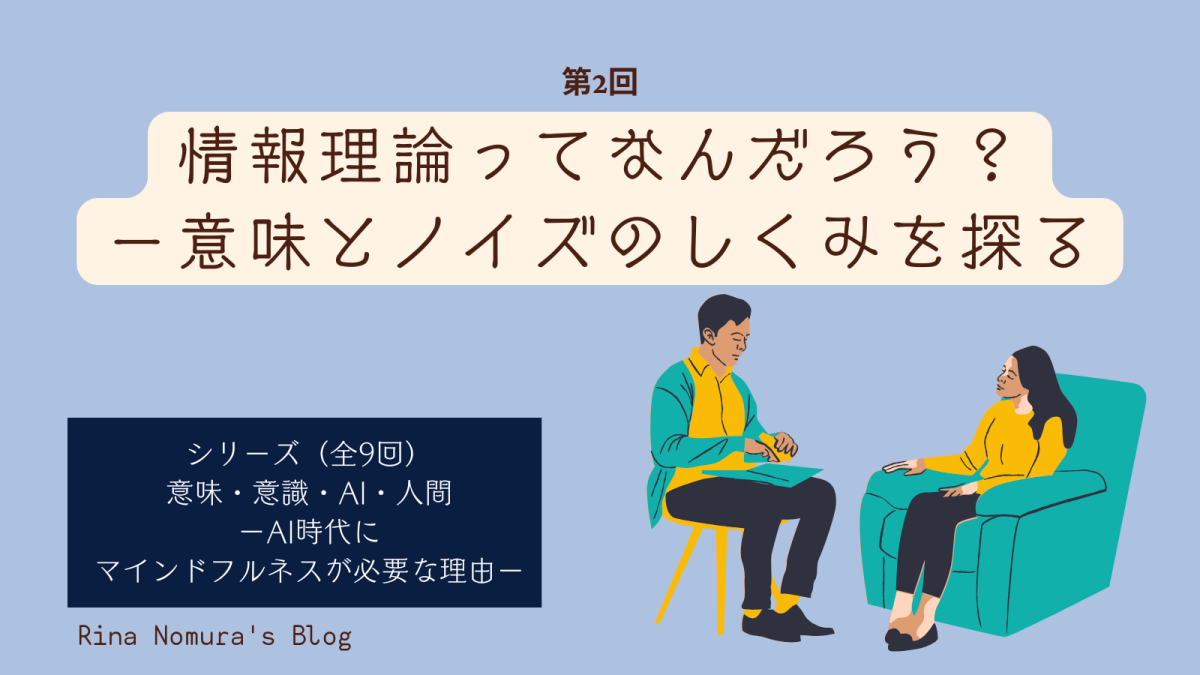
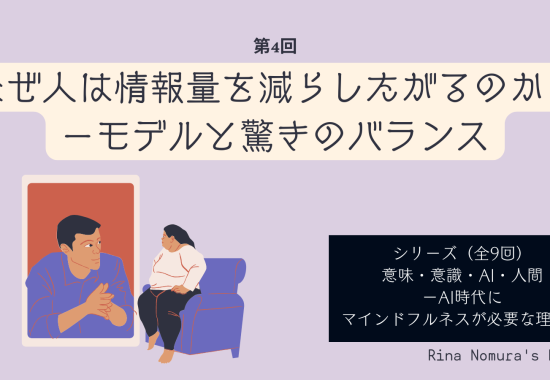
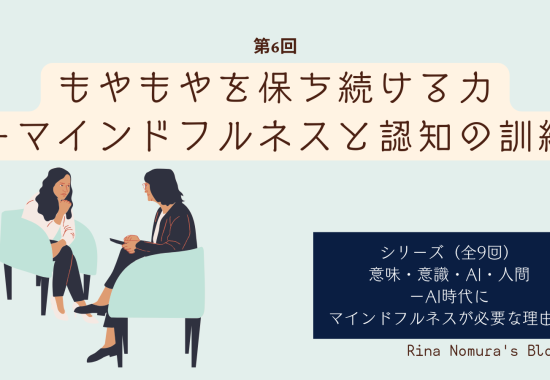
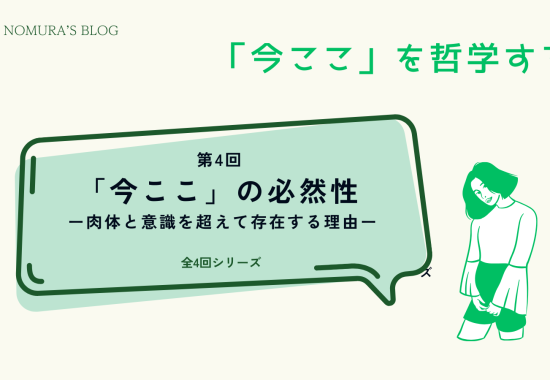
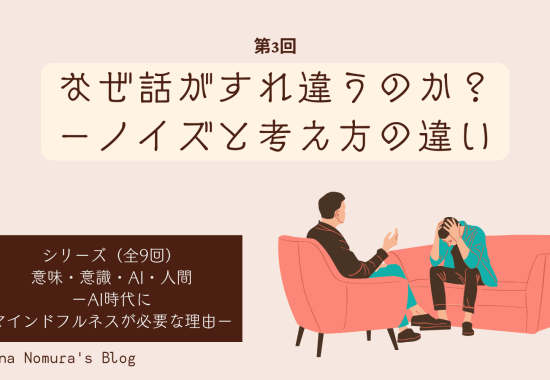
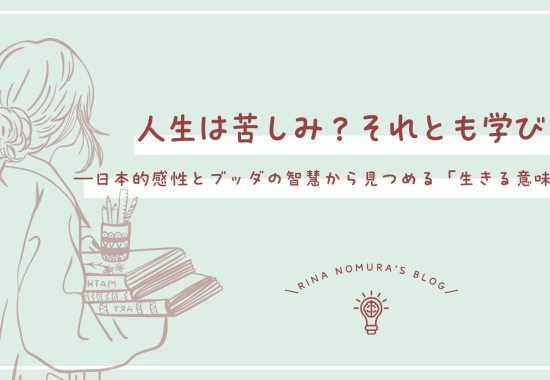
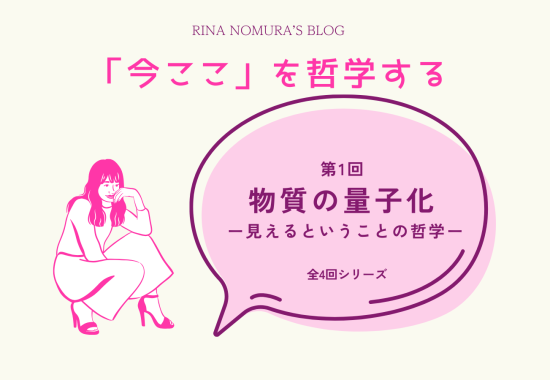
この記事へのコメントはありません。