第6回:もやもやを保ち続ける力 ー マインドフルネスと認知の訓練
【シリーズエッセイ(全9回)】意味・意識・AI・人間ーAI時代にマインドフルネスが必要な理由ー
これまで、「すぐにわかろうとすること」の危うさについて考えてきました。
今回のテーマは、さらに一歩進めて、わからなさ(もやもや)をどう保ち続けるか、
そしてそのために役立つマインドフルネスについて掘り下げます。
人間の脳は、不確かな状態をできるだけ早く解消しようとする性質を持っています。
これは、脳がエントロピー(混沌)を減らす方向に自然に働くからです。
不確かな状況は、脳にとってストレスであり、エネルギーコストが高い。
だから私たちは、無意識のうちに「すぐに答えを出したい」「結論づけたい」と願ってしまうのです。
この傾向は、**予測符号化理論(Predictive Coding Theory)**でも説明されています。
脳は常に環境に対して予測を立て、実際の感覚入力との差分(予測誤差)を最小限に抑えようとします(Friston, 2005)。
しかし、深い理解に至るためには、
この「すぐに解決したい」という衝動に抵抗する必要があります。
わからないことに直面したとき、
-
すぐに判断を下さず
-
すぐにラベリングせず
-
モヤモヤをそのまま保つ
そうした態度が、本当の意味での新しい気づきや創造につながっていきます。
では、どうすればこの「もやもやを保ち続ける力」を育てることができるのでしょうか?
ここで登場するのが、マインドフルネスです。
マインドフルネスとは、
**「今この瞬間に起きていることを、評価せずに観察する態度」**を指します。
たとえば、
-
浮かんでくる思考をすぐに善悪で判断せず
-
感情の波にすぐに巻き込まれず
-
身体の感覚や呼吸を、ただあるがままに感じ取る
といった実践を通して、
私たちは「判断したい」「すぐ結論づけたい」という脳のクセを和らげることができます。
近年の研究でも、マインドフルネス実践は認知的柔軟性を高め、
反応的な思考パターンを抑える効果があることが報告されています(Tang, Hölzel, & Posner, 2015)。
つまり、マインドフルネスは単なるリラクゼーション法ではなく、
わからなさに耐えるための知的・精神的トレーニングにもなり得るのです。
もやもやを抱えることは、決して「何もしない」ことではありません。
むしろ、「まだ名前がついていないもの」「まだ意味づけられていないもの」を
焦らずに見守る、高度な認知的営みなのです。
急がず、焦らず、モヤモヤを抱えたままにしておくこと。
そこから、本当に新しい理解が育っていくのです。
次回(第7回)では、
「AIは『意味』を理解しているのか?」という問いを出発点に、
人間とAIの根本的な違いについて考えていきます。
ぜひ引き続きご覧ください!
参考文献
Friston, K. (2005). A theory of cortical responses. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 360(1456), 815–836. https://doi.org/10.1098/rstb.2005.1622
Tang, Y. Y., Hölzel, B. K., & Posner, M. I. (2015). The neuroscience of mindfulness meditation. Nature Reviews Neuroscience, 16(4), 213–225. https://doi.org/10.1038/nrn3916

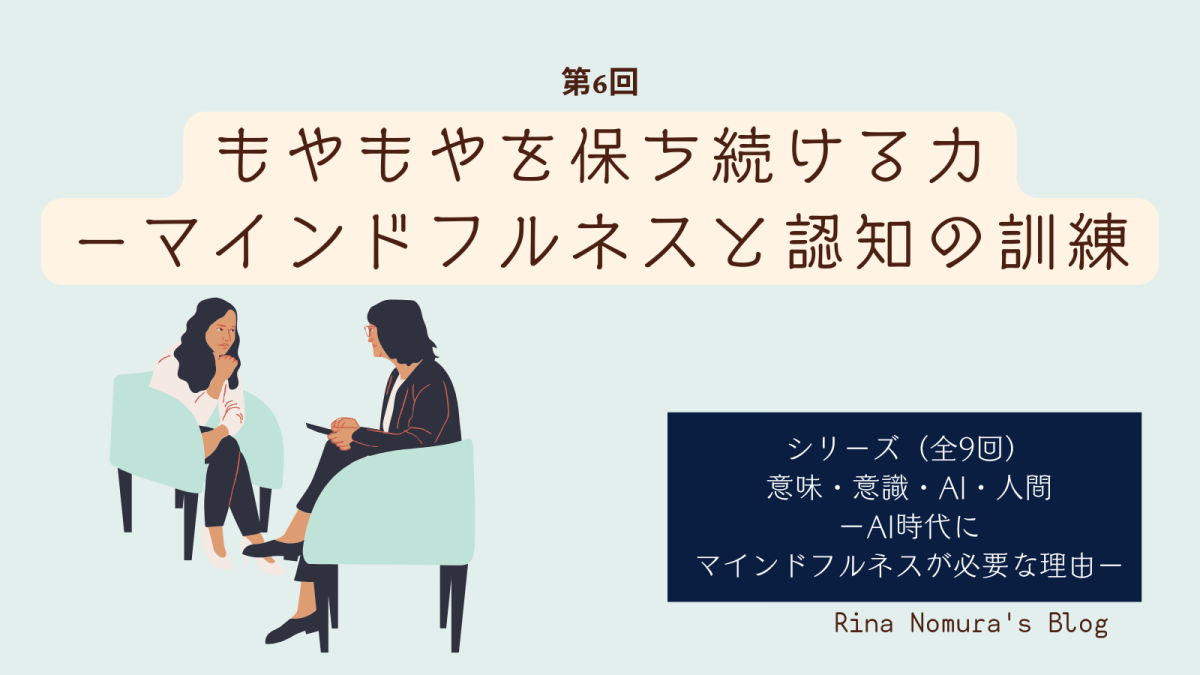
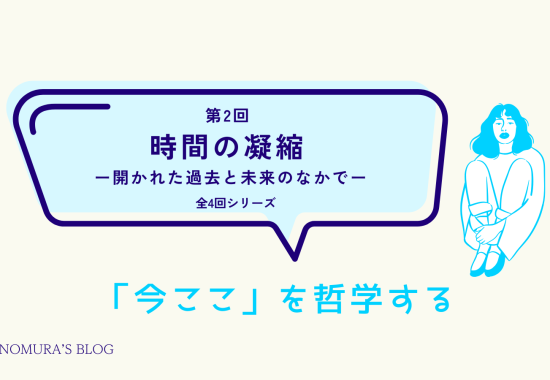
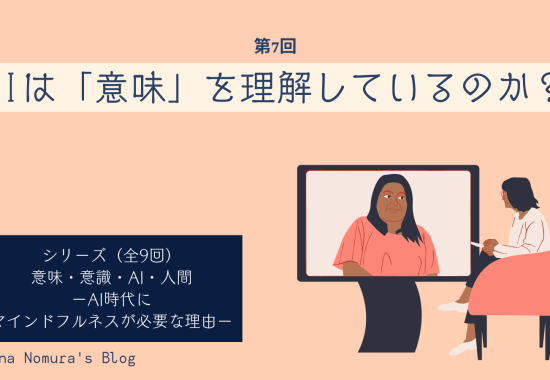

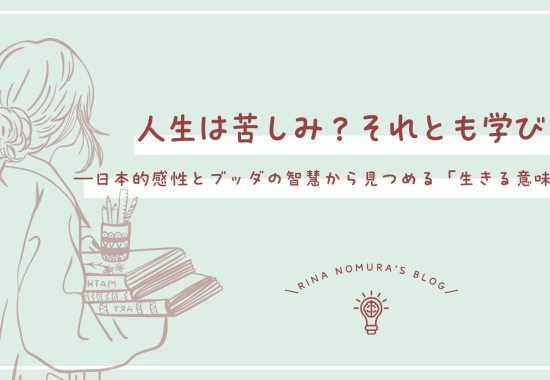
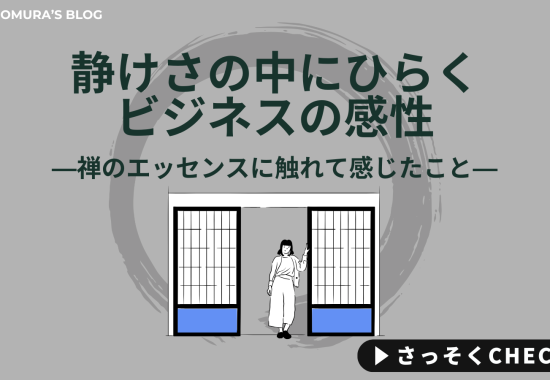
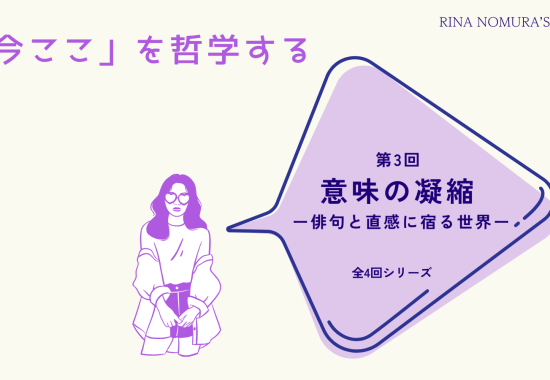
この記事へのコメントはありません。