第3回:なぜ話がすれ違うのか? ー ノイズと考え方の違い
【シリーズエッセイ(全9回)】意味・意識・AI・人間ーAI時代にマインドフルネスが必要な理由ー
前回までに、情報処理理論において「情報量とは予測のしにくさ」であり、
「意味そのもの」には踏み込まないことを確認してきました。
では、私たち人間同士が会話をするとき、なぜしばしばすれ違いが起こるのでしょうか?
その鍵を握るのが、「ノイズ」と「考え方の違い」です。
まず、ノイズとは、単に技術的なエラーを指すだけではありません。
コミュニケーションにおけるノイズは、次の4種類に分類されています(Adler et al., 2021)。
-
物理的ノイズ(Physical Noise):周囲の騒音や電波障害など、環境による妨害
-
生理的ノイズ(Physiological Noise):疲労や体調不良など、身体状態による影響
-
心理的ノイズ(Psychological Noise):怒りや不安、ストレスといった感情の影響
-
意味的ノイズ(Semantic Noise):言葉の意味のズレや文化的背景による誤解
たとえば、周囲が騒がしければ、話の内容が聞き取れなくなる(物理的ノイズ)。
体調が悪ければ、相手の話に集中できない(生理的ノイズ)。
心が不安定なときは、ネガティブに受け止めやすくなる(心理的ノイズ)。
言葉の定義が異なれば、意図とは違った意味で受け取られてしまう(意味的ノイズ)。
こうしたさまざまなノイズが、日常のすれ違いを引き起こします。
さらに重要なのは、
私たちが同じ言葉を使っていても、**それぞれ異なる「世界の見方(モデル)」**を持っていることです。
たとえば、「がんばって」という言葉。
-
励ましと受け取る人もいれば、
-
プレッシャーに感じる人もいる。
-
ときには「追い詰められている」と感じる人さえいます。
つまり、同じ情報でも、受け手の経験、文化、価値観によって、意味が大きく変わるのです。
また、感情的なノイズもすれ違いを深めます。
疲れていたり、不安だったりすると、
相手の言葉を素直に受け取ることが難しくなり、意図しない誤解が生じやすくなります。
ここで大切なのは、
すれ違いを単なる誤解や失敗と捉えるのではなく、
互いの背景や前提が違うのだという前提に立つことです。
違いを認めることで、対話のあり方は大きく変わります。
「なぜ伝わらないのか」と責めるのではなく、
「どんな見方がそこにあるのか」を探ろうとする姿勢が、
ノイズを超えて、意味を育てる力へとつながっていきます。
意味を伝えるとは、
-
完璧な伝達を目指すことではなく、
-
ノイズを受けとめ、違いを理解しようとすること。
-
そしてそこから新しい意味を立ち上げること。
ノイズをゼロにすることはできません。
けれど、ノイズを恐れず、違いを豊かさとして受けとめることで、
私たちはより深い対話を育んでいけるのです。
次回(第4回)では、
「なぜ人は情報量を減らしたがるのか?」というテーマを出発点に、
「モデルと驚きのバランス」について探っていきます。
ぜひ引き続きご覧ください!
参考文献
Adler, R. B., Rosenfeld, L. B., & Proctor, R. F. (2021). Interplay: The process of interpersonal communication (15th ed.). Oxford University Press.
Shannon, C. E. (1948). A mathematical theory of communication. Bell System Technical Journal, 27(3), 379–423. https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x

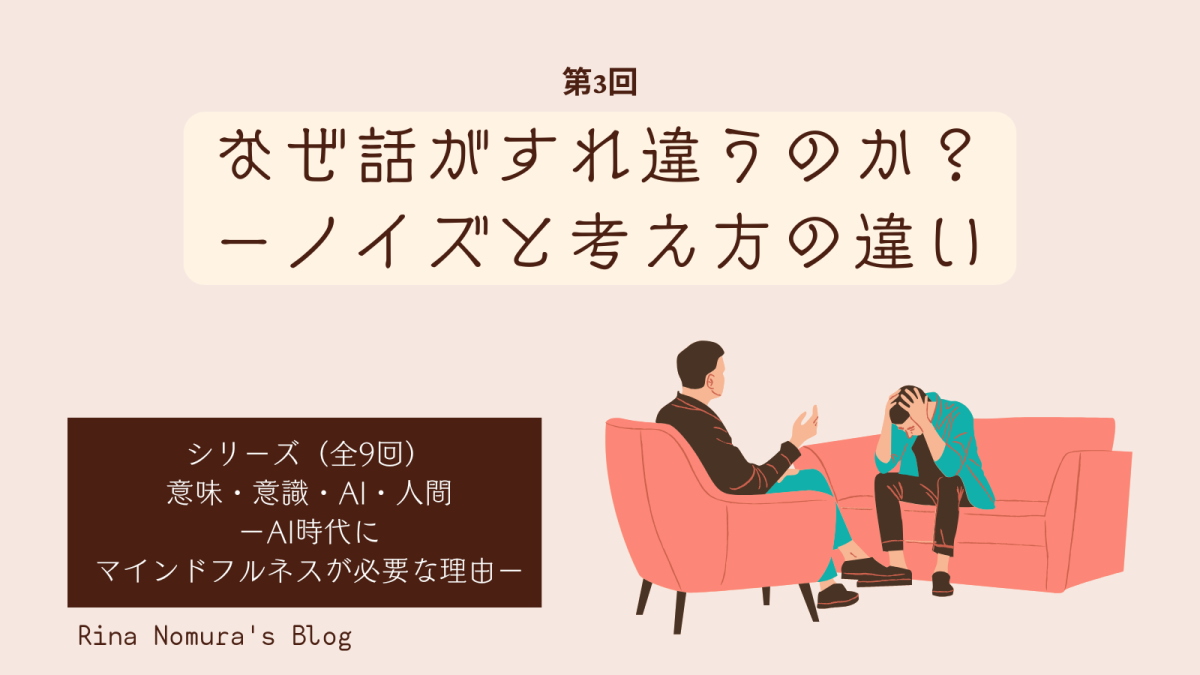
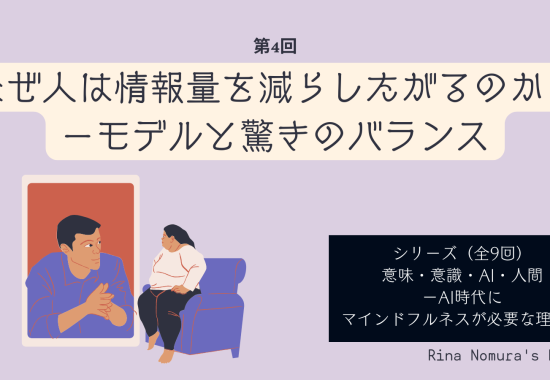
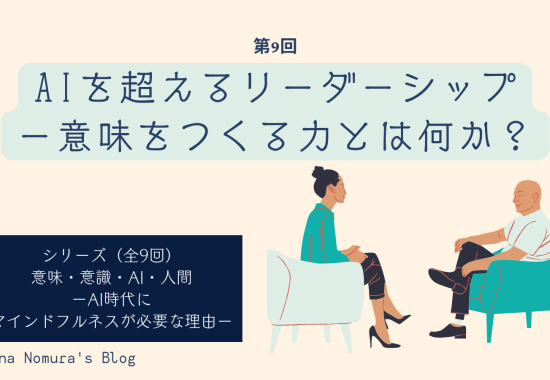
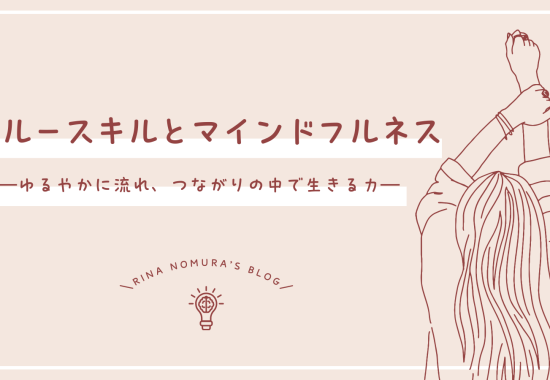
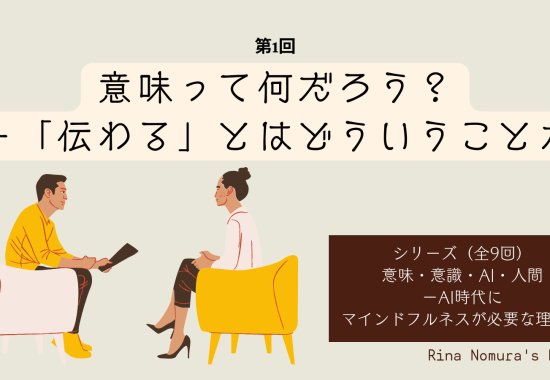
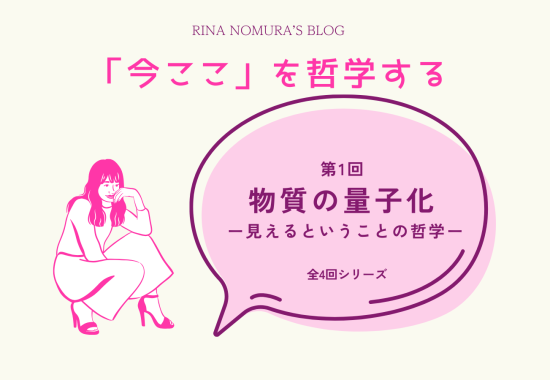
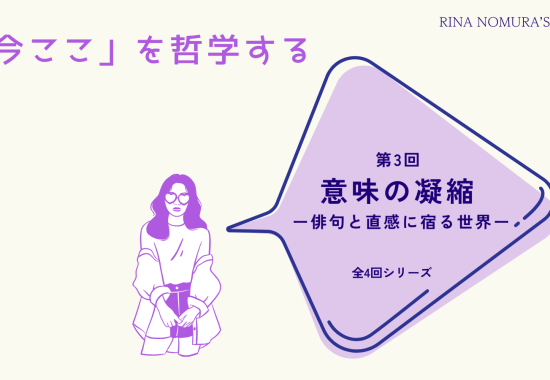
この記事へのコメントはありません。