静けさの中にひらくビジネスの感性─禅のエッセンスに触れて感じたこと
「より最適な選択をしなければ」「もっとスピーディーに決断しなければ」──そんな焦りに包まれた日々を、私たちは生きています。AIやビッグデータが意思決定の一部を担う今、便利さの一方で、自分の感覚や判断に自信が持てなくなっている方も多いのではないでしょうか。
ビジネスの現場では、知識や情報、数字や論理といった「言語化されたもの」が重視されがちです。たしかに、それらは意思決定や戦略を考える上で欠かせない要素です。でも一方で、言葉にならないもの──感覚や身体の声、場の空気といった非言語的な情報も、私たちは日々確かに受け取っています。私自身、瞑想やヨガの実践を通して、頭で「考える」だけでは届かない気づきに何度も出会ってきました。静かに呼吸に意識を向けていると、ふと身体が緩んだ瞬間に、今の自分の状態や、見過ごしていた感情に気づくことがあります。それは、言葉よりも先に、身体や意識がキャッチしていた情報だったのだと感じます。「知ること」も、「感じること」も、どちらも私たちにとって大切な知性なのだと思います。
そんな体験の中で、改めて「禅的な知恵」は、ビジネスにおいても私たちに大切な示唆を与えてくれると感じるようになりました。以下に、その気づきをいくつかシェアしたいと思います。
日々、膨大な情報と無数の選択肢の中にいると、本当に大切なものが見えにくくなってしまいます。そんなときに必要なのは、「何を足すか」ではなく、「何を引くか」の視点です。
Appleの創業者スティーブ・ジョブズが禅に傾倒していたのは有名な話です。彼の「シンプルであることは、究極の洗練である」という言葉は、まさに禅の精神そのもの。製品のデザインや機能はもちろん、彼自身の意思決定のあり方にも、禅の影響が色濃く反映されていたように感じます。
私たちも、判断に迷ったときこそ、外の情報ではなく、自分の内側に耳を傾ける時間が必要なのかもしれません。
「直感」は、何か特別な才能のように思われがちですが、実は誰もが持っている感覚です。京セラの創業者・稲盛和夫さんも「人として正しいことをする」ことを経営の軸に据えていました。そこには、計算ではたどり着けない、研ぎ澄まされた感性がありました。
心理学や神経科学の研究でも、禅的な瞑想や内省の実践が、無意識下での情報処理能力を高めることが示されています。つまり、静かな時間は「直感という知性」を育む場でもあるのです。
私も、答えを出そうと必死になっていた時より、ふと一息ついたときに、大切なひらめきが浮かぶ経験を何度もしてきました。そんな瞬間には、思考では届かない深い場所とつながっている感覚があります。
ビジネスの現場でも「マインドフルネス」が定着しつつあります。今この瞬間に意識を向け、集中力やストレス耐性を高めるための実践として、多くの企業が研修に取り入れています。
一方で、禅のアプローチは少し違います。呼吸や姿勢に意識を向けることもありますが、それ以上に、「思考や感情にとらわれない心」を養うことを重視します。考えることを止めるのではなく、考えに巻き込まれない心のあり方を育てる──そんなイメージです。
私自身は、どちらが優れているという話ではなく、それぞれに違った良さがあると感じています。マインドフルネスは現代的な文脈に合った入口として親しみやすく、禅はさらに深い洞察と変容の余地を与えてくれる存在。どちらも、私たちの「今、ここ」に気づきをもたらしてくれる、大切な実践です。
松下幸之助さんが「素直な心こそ経営の原点」と語っていたように、真のリーダーシップは、どれだけ知識を持っているかではなく、どれだけ自分自身を整えているかにかかっていると思います。
変化が激しい時代だからこそ、外に振り回されない内なる軸が求められます。そのためには、ただ何かを「する」のではなく、あえて「立ち止まる」時間が必要です。
禅の教えが示すように、沈黙の中でこそ、見えてくるものがあります。ジョブズが禅寺に通ったように、ビル・ゲイツが読書と孤独の思索の時間を大切にしたように、自分の内側に静けさを取り戻すことは、未来を切り拓くための「準備」でもあるのです。

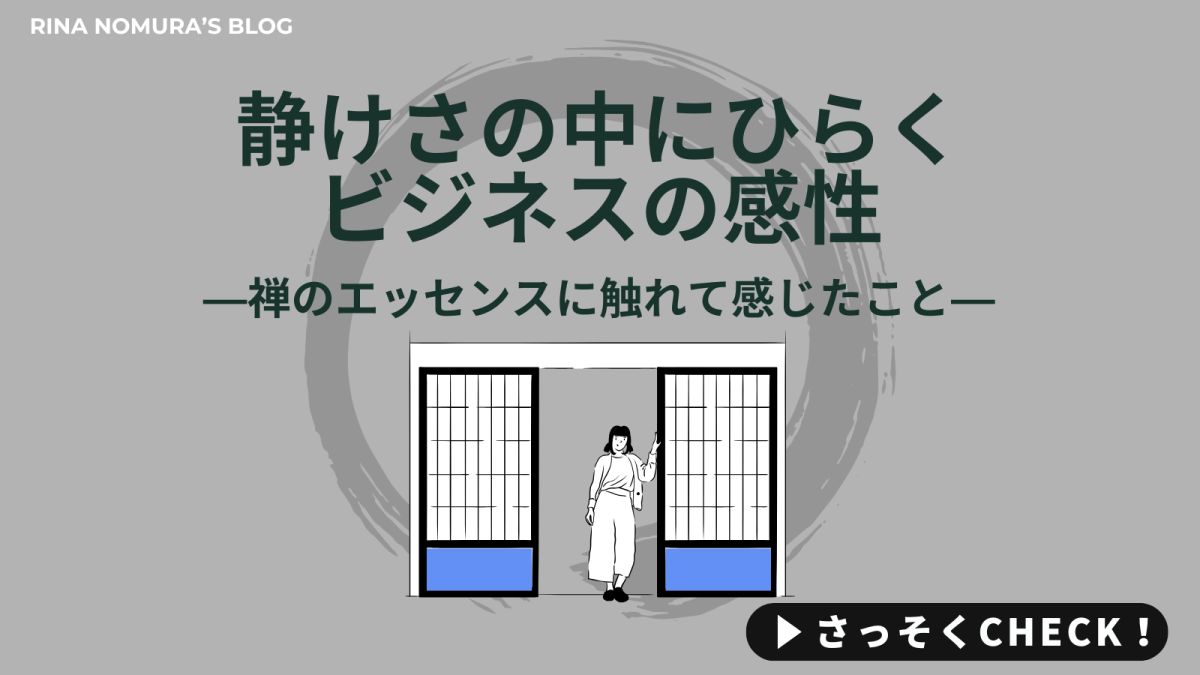
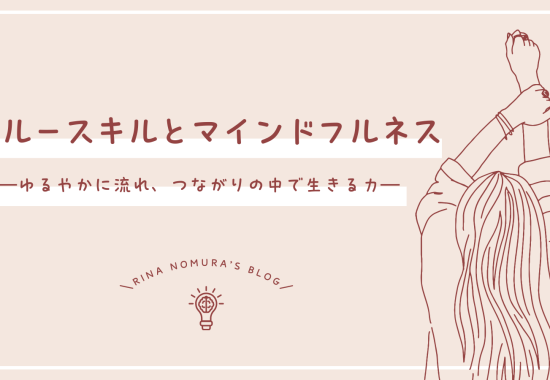

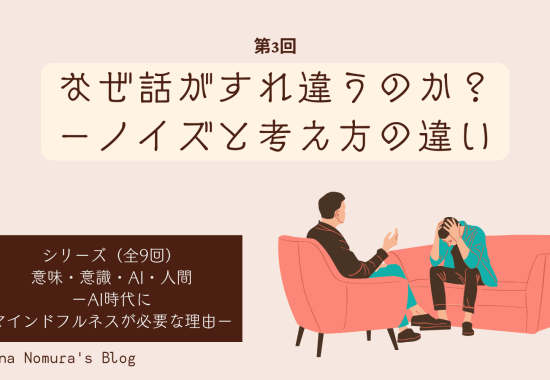
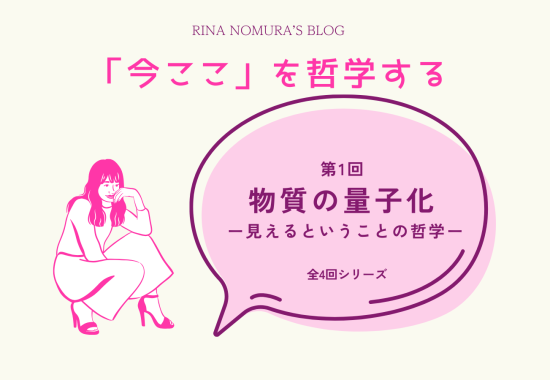
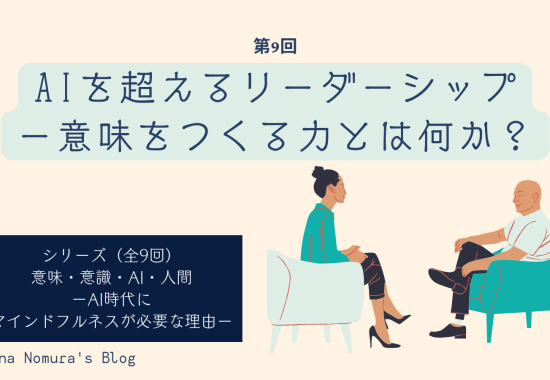
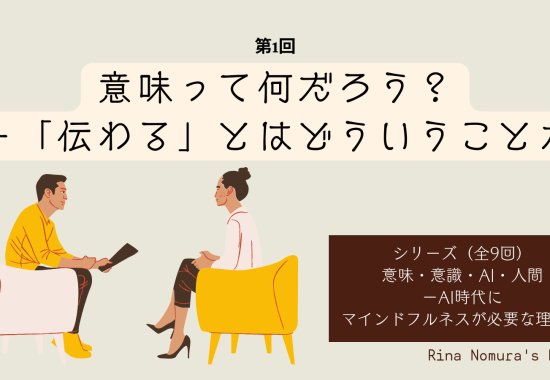
この記事へのコメントはありません。